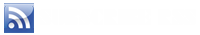гҖҺгғҲгӮҘгғігғҮIгҖҸгҒ«з¶ҡгҒ„гҒҰеҮәгҒ•гӮҢгҒҹжң¬жӣёгӮӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢе…¬й–ӢжҺҲжҘӯгҒЁи¬ӣжј”иЁҳйҢІйӣҶгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е№јзЁҡең’гҒ§гҒ®гҖҢгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„жңқй®®гҒЁгҒ®еҮәдјҡгҒ„гӮ’гҖҚгҒЁйЎҢгҒ•гӮҢгҒҹе®ҹи·өгҒҜгҖҒе°ұеӯҰеүҚгҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҒ®гҖҒйҒҠгҒігӮ’йҖҡгҒ—гҒҰиҮӘ然гҒӘеҪўгҒ§гҖҒжңқй®®гҒЁгҒ®иұҠгҒӢгҒӘеҮәдјҡгҒ„гӮ’жЁЎзҙўгҒҷгӮӢиІҙйҮҚгҒӘгҒЁгӮҠгҒҸгҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…Ёжңқж•ҷгҒ§гӮӮгҖҒ93е№ҙгҒ®дә¬йғҪеӨ§дјҡгҒӢгӮүе°ұеӯҰеүҚж•ҷиӮІгҒ®еҲҶ科дјҡгҒҢгӮӮгҒҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒеӨ§дјҡгҒ§гҒҜгҒҳгӮҒгҒҰе°ұеӯҰеүҚгҒ®зҸҫе ҙгҒӢгӮүе ұе‘ҠгҒҢгҒӮгҒҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ90е№ҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®е ұе‘ҠиҖ…гҒ®гҒқгҒ®еҫҢгҒ®е®ҹи·өгҒҢгҒ“гӮҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
д»–гҒ«гҖҢж–ҮеҢ–гҒ«иҰӘгҒ—гӮӮгҒҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҢгғҸгғігӮ°гғ«гӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖҚгӮ„гҖҒжӯҙеҸІгҒӢгӮүгҒҜгҖҢз§ҖеҗүгҒ®жңқй®®дҫөз•ҘпјҲеЈ¬иҫ°еҖӯд№ұпјүгҖҚгҒ®жҺҲжҘӯиЁҳйҢІгҒӘгҒ©гҒҢеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
и¬ӣжј”йҢІгҒ®ж–№гҒҜгҖҒи—ӨеҺҹе…Ёжңқж•ҷдјҡй•·гҒҢгҖҢзңҢеӨ–ж•ҷгҒ«жңӣгӮҖгӮӮгҒ®гҖҚгҒЁйЎҢгҒ—гҒҰгҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҖҒе…ЁеӣҪж°‘й—ҳйҖЈдәӢеӢҷеұҖй•·гҒ®еҫҗжӯЈзҰ№ж°ҸгҒ®гҖҢж—Ҙжң¬гҒ®ж•ҷеё«гҒ«жңҹеҫ…гҒҷгӮӢгҖҚгӮӮгҒ®гҖҒз”°жё•дә”еҚҒз”ҹеҘҲиүҜж•ҷиӮІеӨ§ж•ҷжҺҲгҒ®зңҢеӨ–ж•ҷзөҗжҲҗз·ҸдјҡгҒ§гҒ®гӮӮгҒ®гҒ®пј“жң¬гҒҢеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҢиЁјиЁҖйҢІгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢжңқй®®дәәеј·еҲ¶йҖЈиЎҢгҒ®иЁјиЁҖгҖҚгҒҢгҒҠгҒ•гӮҒгӮүгӮҢгҖҒеҚҠдё–зҙҖеүҚгҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®йЈӣиЎҢе ҙе»әиЁӯгӮ’еј·гҒ„гӮүгӮҢгҒҹйҮ‘гҒ•гӮ“гғ»е®ӢгҒ•гӮ“гҒ®иІҙйҮҚгҒӘжӯҙеҸІзҡ„иЁјиЁҖгҒҢиЁҳйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иЁјиЁҖгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«ж•ҷжқҗеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒгҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ еј·еҲ¶еҠҙеғҚз·ЁгҖҸгҒ«дёҖйғЁгҒҠгҒ•гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢжҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖӮ
пјўпј•еҲӨгҖҖ98гғҡгғјгӮё
й ’дҫЎгҖҖ800еҶҶ
еңЁеә«гҒӘгҒ—
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгғҲгӮҘгғігғҮIIгҖҖпјҚе…¬й–ӢжҺҲжҘӯгҒЁи¬ӣжј”иЁҳйҢІйӣҶпјҚгҖҸ
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгғҲгӮҘгғігғҮIIгҖҖпјҚе…¬й–ӢжҺҲжҘӯгҒЁи¬ӣжј”иЁҳйҢІйӣҶпјҚгҖҸ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгғҲгӮҘгғігғҮв… гҖҖпјҚгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ жҺҲжҘӯе®ҹи·өгӮ’дёӯеҝғгҒ«пјҚгҖҸ
гҖҢгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ жҺҲжҘӯе®ҹи·өгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҚгҒЁеүҜйЎҢгҒ•гӮҢгҒҹжң¬жӣёгҒҜгҖҒе°Ҹгғ»дёӯгҒ®еӯҰж ЎзҸҫе ҙгҒ§гҒ®гҖҒжҺҲжҘӯе®ҹи·өгҒЁи¬ӣжј”йҢІгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
жҺҲжҘӯиЁҳйҢІгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҸпјҲжӯҙеҸІз·ЁпјүгҒЁгҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гғ»гғҺгғӘгҖҸгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжңқй®®ж–ҷзҗҶгҒ®гҖҢгғҲгғғгӮҜгӮ’гҒӨгҒҸгӮҚгҒҶгҖҚгӮ„гҖҒе–„йҡЈеҸӢеҘҪгҒ®жӯҙеҸІгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢжңқй®®йҖҡдҝЎдҪҝгҖҚгҖҒиҝ‘д»ЈгҒ®гҖҢеј·еҲ¶йҖЈиЎҢгҖҚгӮ„гҖҒеӨ–еӣҪдәәзҷ»йҢІжі•гҒӘгҒ©гҒ®зҸҫзҠ¶гӮ’гҖҢеҗҢеҢ–гҒЁжҺ’еӨ–гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰдё»йЎҢеҢ–гҒ•гҒӣгҒҹжҺҲжҘӯгҒӘгҒ©гҒҢеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒи¬ӣжј”иЁҳйҢІгҒҜгҖҒйҹ“еӣҪгҒ®ж•ҷиӮІеҠҙеғҚиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢй„ӯе…ғж°ҸгҒ®гҖҢжӯҙеҸІиӘҚиӯҳгҒ®иҗҪе·®гӮ’еҹӢгӮҒгӮӢгҖҚгҒЁйЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁйҹ“еӣҪгҒ®иҝ‘гғ»зҸҫд»ЈеҸІж•ҷиӮІгҒ®й–“гҒ«гҒӮгӮӢи«ёе•ҸйЎҢгӮ’гғҶгғјгғһгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҖҒйҮ‘дә•е…Ёжңқж•ҷдәӢеӢҷеұҖй•·гҒҢгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰ第еҚҒеӣһзҰҸеІЎеӨ§дјҡгҒ®е…Ҙй–ҖеҲҶ科дјҡгҒ§и©ұгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢж—Ҙжң¬гҒЁжңқй®®гҒ®й–ўдҝӮеҸІгҒ«еӯҰгҒ¶гҖҚгҒЁйЎҢгҒ—гҒҰгҖҒеңЁж—ҘгӮ’гҒЁгӮӮгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жӯҙеҸІе…Ҙй–ҖгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҒҠгҒ•гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
и¬ӣжј”гҒӢгӮүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁйҹ“еӣҪгҒ®й–“гҒ«гҒӮгӮӢжӯҙеҸІиӘҚиӯҳгҒ®иҗҪе·®гҒҢжө®гҒҚеҪ«гӮҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ—гҖҒгҒ„гҒҫгҒҫгҒ§зҹҘгӮүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ“гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж—Ҙжң¬гҒЁжңқй®®гҒ®й–ўдҝӮеҸІгҒҢжө®гҒӢгҒігҒӮгҒҢгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе®ҹи·өиЁҳйҢІгҒӢгӮүгҒҜгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ зҸҫе ҙгҒ§гҒЁгӮҠгҒҸгӮҒгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәәгҖ…гҒ«иІҙйҮҚгҒӘзӨәе”ҶгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮжң¬жӣёгҒӢгӮүеӨҡгҒҸгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢеӯҰгҒ№гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
B5еҲӨгҖҖ89гғҡгғјгӮё
й ’дҫЎгҖҖ700еҶҶ
еңЁеә«гҒӘгҒ—
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгғҲгӮҘгғігғҮв… гҖҖпјҚгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ жҺҲжҘӯе®ҹи·өгӮ’дёӯеҝғгҒ«пјҚгҖҸ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҖпјҚеј·еҲ¶еҠҙеғҚз·ЁпјҚгҖҸ
жҲҰеҫҢеҚҠдё–зҙҖгҒҢгҒҹгҒЈгҒҹд»ҠгӮӮгҖҒе…ЁеӣҪеҗ„ең°гҒ«жҲҰдәүгҒ®еӮ·з—•гҒҢж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҢж¬ЎгҒ®дё–д»ЈгҒ«гҒҫгҒ§иӘһгӮҠз¶ҷгҒҢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҜйҷҗгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮҖгҒ—гӮҚгҖҒйҡ гҒ•гӮҢгҒҹгҒҫгҒҫгҒ§гҖҒең°е…ғгҒ®дәәгӮӮзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҒ«ж”ҫзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ•гҒҲж•°еӨҡгҒҸгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӯҙеҸІгҒ®й—ҮгҒ«еҹӢгӮӮгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹеј·еҲ¶йҖЈиЎҢгғ»еј·еҲ¶еҠҙеғҚгҒ®жӯҙеҸІгӮ’зҷәжҺҳгҒ—гҒҰгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«ж•ҷжқҗеҢ–гӮ’и©ҰгҒҝгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢжң¬жӣёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еҘҪи©•гҒ®гҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҸгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®дёҖеҶҠгҒЁгҒ—гҒҰеҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹжң¬жӣёгҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸдәҢгҒӨгҒ®йғЁеҲҶгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҖгҒӨгҒҜгҖҒжҲҰдәүжң«жңҹгҒ«жө·и»ҚйЈӣиЎҢе ҙе»әиЁӯгҒ«гҒӢгӮҠгҒ гҒ•гӮҢгҒҹжңқй®®дәәеҠҙеғҚиҖ…гҒ®жӯҙеҸІгӮ’гҒӮгҒҚгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒеј·еҲ¶йҖЈиЎҢгғ»еј·еҲ¶еҠҙеғҚгҒ®е®ҹж…ӢгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒӮгҒ’гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ«гҖҢжӯҙеҸІгӮ’гӮҸгҒҷгӮҢгҒӘгҒ„гҒ§гҖҚгҒЁиЁҙгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒҜгҖҒең°дёӢиҰҒеЎһгҒ®е»әиЁӯгҒ«гҒӢгӮҠгҒ гҒ•гӮҢгҒҹжңқй®®дәәе…өеЈ«гҒ®жӯҙеҸІгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒҢиҝҪдҪ“йЁ“гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҠҮеҢ–гҒ—гҒҹгӮ·гғҠгғӘгӮӘгӮ’дё»гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҸІе®ҹгҒ®й–ўйҖЈиіҮж–ҷгҒҢеҸҺгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҠҮгҒҜгҒҷгҒ§гҒ«еӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҪ•еӣһгҒӢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«дёҠжј”гҒ•гӮҢгҖҒеҘҪи©•гӮ’гҒҜгҒҸгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҖҒеҝҳгӮҢгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„жӯҙеҸІгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢеҝғгҒ«гҒҚгҒ–гӮҖгҒ№гҒҚгҖҚдәӢе®ҹгҒ®ж•ҷжқҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
B5еҲӨгҖҖ59гғҡгғјгӮё
й ’дҫЎгҖҖ700еҶҶ
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҖпјҚеј·еҲ¶еҠҙеғҚз·ЁпјҚгҖҸ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·Ё гҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҖпјҚйҹіжҘҪз·ЁпјҚгҖҸ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒиҘҝжҙӢгҒ®йҹіжҘҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеӯҰж ЎгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҒөгӮҢгӮӢж©ҹдјҡгҒҢзөҗж§ӢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ«гҖҒйҡЈгҒ®еӣҪгғ»жңқй®®гҒ®йҹіжҘҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жҺҘгҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ®гҒҠгҒӢгҒ—гҒ•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ•гҒҲгҖҒж°—гҒҘгҒ„гҒҰгӮӮгҒ“гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жң¬гҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘзҸҫзҠ¶гӮ’гҒӘгӮ“гҒЁгҒӢеӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁгҒ®жҖқгҒ„гҒӢгӮүз”ҹгҒҝеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҚҳгҒӘгӮӢжӯҢйӣҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжңҖеҲқгҒҜгҖҢгӮӘгғігғһгҒЁйҒӢеӢ•дјҡгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзү©иӘһгҒӢгӮүгҒҜгҒҳгҒҫгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒжңқй®®гҒ®жҘҪеҷЁгғҒгғЈгғігӮ°гҒ®жј”еҘҸгҒ®гҒ—гҒӢгҒҹгҖҒйҒӢеӢ•дјҡгҒ§гҒ®иҫІжҘҪгҖҒгӮөгғігғўгӮ„гӮҪгӮҙгҒ®з°ЎеҚҳгҒӘгҒӨгҒҸгӮҠгҒӢгҒҹзӯүгҖ…гҒҢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҖҢгӮўгғӘгғ©гғігҖҚгӮ„гҖҢгғҢгғігғҢгғігғҢгғігҖҚгҖҒгҖҢгӮўгғ—гғӯгҖҚзӯүгҖ…гҒ®жӯҢгҒҢгҖҒжҢҜгӮҠд»ҳгҒ‘гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҖҒзҸҫе ҙгҒ§гҒҷгҒҗдҪҝгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«е·ҘеӨ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢгғүгғ¬гғҹгҒ®жӯҢгҖҚгӮ„гҖҢгӮЁгғјгғҮгғ«гғҜгӮӨгӮ№гҖҚгҒӘгҒ©гҒ®жңүеҗҚгҒӘжӯҢгӮӮжңқй®®иӘһгҒ§зҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢгғҸгғҠгғӯпјҲгғҜгғігӮігғӘгӮўгғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гҒ®гғҶгғјгғһгӮҪгғігӮ°пјүгҖҚгҖҒгҖҢгӮ»гӮҝгғӘгғ§гғіпјҲйіҘзҜҖпјүгҖҚгҖҒгҖҢгғқгғігӮҪгғігғ•гӮЎпјҲйіід»ҷиҠұпјүгҖҚзӯүгӮӮеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзӣӣгӮҠгҒ гҒҸгҒ•гӮ“гҒ®ж•ҷжқҗгҒЁгҒ„гҒҲгӮҲгҒҶгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒе…ғгғ»жңқй®®дәәеј·еҲ¶еҫ“и»Қж…°е®үе©ҰгҒ®иЁјиЁҖгҒ§гҖҒгҖҢгӮ·гғігӮ»гӮҝгғӘгғ§гғіпјҲиә«дё–жү“йҲҙпјүгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиӘһгӮүгӮҢгҒҹдёӯгҒӢгӮүгҒІгҒЁгҒӨгҒ®и©©гҒҢжңҖеҫҢгҒ«гҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒ92е№ҙ12жңҲгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒҹж—Ҙжң¬гҒ®жҲҰеҫҢиІ¬д»»гӮ’иҝҪеҸҠгҒҷгӮӢеҘҲиүҜз ”дҝ®дјҡгҒ§гҒ®зҷәиЁҖгҒӢгӮүжҺЎгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжҙ»з”ЁгҒҜзҸҫе ҙгҒ®ж•ҷе“ЎгҒ«гҒҫгҒӢгҒӣгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
B5еҲӨгҖҖ88гғҡгғјгӮё
й ’дҫЎгҖҖ900еҶҶ
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·Ё гҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҖпјҚйҹіжҘҪз·ЁпјҚгҖҸ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҖпјҚйҒҠгҒіз·ЁпјҚгҖҸ
жң¬жӣёгҒҜгҖҒгғ‘гғігғҡгғЁгғіпјҲжңқй®®еҮ§пјүгҒ®дҪңгӮҠж–№гӮ’дёӯеҝғгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠгҒҫгҒ§гҖҒгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘдҪңгӮҠж–№гӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғЁгғігҒ®еҲ¶дҪңгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгҒЁгӮ“гҒ§гҒҸгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒзңҢеӨ–ж•ҷгҒ§гҒҜзө¶еҜҫгҖҢгҒЁгҒ¶гҖҚгғЁгғігӮ’гӮҒгҒ–гҒ—гҒҰдҪңгӮҠж–№гҒ®з ”究пјҹгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹзөҗжһңгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®йҒҠгҒіз·ЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒгҒҹгҒ гғЁгғігӮ’дҪңгӮӢеҶ…е®№гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮеңЁж—Ҙжңқй®®дәәпј‘дё–гҒ®гғҸгғ©гғңгӮёгҒ®гғ‘гғігғҡгғЁгғігҒ«гҒҫгҒӨгӮҸгӮӢжҖқгҒ„еҮәи©ұгӮ„гҒӮгҒ’ж–№гҒӘгҒ©гӮ’иҒһгҒҚеҸ–гӮҠгҒ—гҖҒгӮ„гҒ•гҒ—гҒ„иӘӯгҒҝзү©гҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®дёӯгҒ§гғҸгғ©гғңгӮёгҒҜгҖҢгҒ“гҒ®еҮ§гҒҜгҖҒгӮҸгҒ—гҒ®еӣҪгҒ®еҮ§гҒҳгӮғгҖҚгҒЁиӘһгӮҠе§ӢгӮҒгӮӢгҖӮз”ҹгҒҫгӮҢж•…йғ·гҒ®жңқй®®гҒ®гғһгӮөгғігҒҜгҖҒеҸЈгҒ§гҒҜиЁҖгҒ„иЎЁгҒӣгҒӘгҒ„гҒӘгҒ„гҒҸгӮүгҒ„зҫҺгҒ—гҒҸгҖҒгғЁгғігӮ’гҒӮгҒ’гӮӢгҒ«гҒҜгӮӮгҒЈгҒҰгҒ“гҒ„гҖӮгғҸгғ©гғңгӮёгҒ®зӣ®гҒҜгҒҡгҒҶгғјгҒЁйҒ гҒҸгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬дәәгҒ®еӯҗгҒ©гӮӮгӮҝгӮҜгғҹгҒҜгҖҢгҒҠгҒҳгҒ„гҒ•гӮ“гҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒ«гҒ„гӮӢгҒ®гҖҚгҒЁе•ҸгҒ„гҒӢгҒ‘гӮӢгҖӮгғҸгғ©гғңгӮёгҒҜгҖҒе…ҲгҒ®жҲҰдәүгҒ®гҒ“гҒЁгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«з„ЎзҗҶзҹўзҗҶйҖЈгӮҢгҒҰгҒ“гӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒеҗҚеүҚгҒҢдәҢгҒӨгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©йқҷгҒӢгҒ«и©ұгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒдәҢдәәгҒ§гӮ„гҒЈгҒЁгҒӮгҒ’гҒҹгғ‘гғігғҡгғЁгғігҒҢй«ҳгҒҸй«ҳгҒҸгҒӮгҒҢгӮӢгҖӮгӮҝгӮҜгғҹгҒҜгҒқгҒЈгҒЁгҖҢгғҸгғ©гғңгӮёвҖҰгҖҚгҒЈгҒҰгҖҒеҝғгҒ®дёӯгҒ§е‘јгӮ“гҒ гҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгғҸгғ©гғңгӮёгҒ®жҖқгҒ„гӮ’еӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ«гҒӨгҒӘгҒҺгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғЁгғідҪңгӮҠгҒ«гҒЁгӮҠгҒҸгӮ“гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„гҖӮд»–гҒ«гӮҸгҒӢгӮҠжҳ“гҒ„гғҰгғігғҺгғӘгҒ®йҒҠгҒіж–№зӯүгӮ’еҸҺйҢІгҖӮ
еңЁеә«гҒӘгҒ—
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺгӮӘгғғгӮұгғҲгғігғ гҖҖпјҚйҒҠгҒіз·ЁпјҚгҖҸ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺе·®еҲҘгҒЁжҺ’еӨ–гӮ’ж’ғгҒӨгҖҖпјҚеҘҲиүҜгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеңЁж—Ҙжңқй®®дәәж•ҷиӮІйҒӢеӢ•гҒ“гҒ®12е№ҙгҒ®жӯ©гҒҝпјҚгҖҸ
1979е№ҙгҒ®е…Ёжңқж•ҷ第1еӣһз ”з©¶еӨ§дјҡгҒӢгӮүгҖҒ90е№ҙгҒ®з¬¬11еӣһеӨ§дјҡгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҒ«жҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҹеҘҲиүҜгҒӢгӮүгҒ®е ұе‘ҠгӮ’йӣҶгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…¬еӢҷе“ЎжҺЎз”ЁгҒ®еӣҪзұҚжқЎй …ж’Өе»ғгҒ®й—ҳгҒ„гҒӢгӮүеҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡзөҗжҲҗгҒҫгҒ§гҒ®гҖҒеҘҲиүҜгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҒгҒ“гҒ®12е№ҙй–“гҒ®еңЁж—Ҙжңқй®®дәәж•ҷиӮІгҒ®жӯ©гҒҝгҒҢжҰӮиҰігҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
зҸҫе ҙгҒ®е®ҹи·өгҒ§гҒҜгҖҒе°ұеӯҰеүҚж®өйҡҺгҒ§гҒ®иҮӘ然гҒӘеҮәдјҡгҒ„гӮ’еүөгӮҠеҮәгҒқгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹе№јзЁҡең’гҒ®гҒЁгӮҠгҒҸгҒҝгӮ„гҖҒе°ҸеӯҰж ЎгҒ§гҒ®зҫҺиЎ“гӮ„йҹіжҘҪгӮ’йҖҡгҒ—гҒҹиұҠгҒӢгҒӘеҮәдјҡгҒ„гҖҒжңқй®®гҒ®зӢ¬жҘҪгҒҫгӮҸгҒ—гӮ„еҮ§гҒӨгҒҸгӮҠгҒӘгҒ©гҒ®йҒҠгҒігӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒ®е°Ҹгғ»дёӯеӯҰж ЎгҒ§гҒ®е®ҹи·өгҖҒгҒҫгҒҹжңқй®®гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®й–ўдҝӮеҸІгӮ’зўәгҒӢгҒ«иӘҚиӯҳгҒ•гҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢе°Ҹгғ»дёӯгғ»й«ҳж ЎгҒ§гҒ®жӯҙеҸІеӯҰзҝ’гҒӘгҒ©еӨҡеҪ©гҒӘеҶ…е®№гҒ®гҒЁгӮҠгҒҸгҒҝгҒҢеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒй«ҳж Ўз”ҹдәӨжөҒдјҡгӮҪгғҖгғігҒ®жӯ©гҒҝгӮ„ж„ҸиӯҳиӘҝжҹ»гғ»е®ҹж…ӢиӘҝжҹ»гҒ®гҒЁгӮҠгҒҸгҒҝгҖҒжң¬еҗҚе®ЈиЁҖгҖҒеӨңй–“дёӯеӯҰгҖҒзңҢгҒ®жҢҮйҮқзӯ–е®ҡгҒҫгҒ§гҒ®зөҢйҒҺзӯүгҖ…гҖҒдёҖдәәгҒ®еӯҗгҒ©гӮӮгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’гҒӮгҒҰгҒҹгӮӮгҒ®гҒӢгӮүгҖҒйӣҶеӣЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҒЁгӮҠгҒҸгҒҝгҒӘгҒ©иұҠеҜҢгҒӘе®ҹи·өиЁҳйҢІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгҒ“гҒ®еҶҠеӯҗгҒҜгҖҒпј’еӣһзӣ®гҒ®е…Ёжңқж•ҷеҘҲиүҜеӨ§дјҡй–ӢеӮ¬гӮ’иЁҳеҝөгҒ—гҒҰз·ЁйӣҶгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’д»ҳиЁҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ
B5еҲӨгҖҖ169гғҡгғјгӮё
й ’дҫЎгҖҖ1200еҶҶ
еҘҲиүҜзңҢеӨ–еӣҪдәәж•ҷиӮІз ”究дјҡз·ЁгҖҺе·®еҲҘгҒЁжҺ’еӨ–гӮ’ж’ғгҒӨгҖҖпјҚеҘҲиүҜгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеңЁж—Ҙжңқй®®дәәж•ҷиӮІйҒӢеӢ•гҒ“гҒ®12е№ҙгҒ®жӯ©гҒҝпјҚгҖҸ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
дёӢд№Ӣеә„жӯҙеҸІз ”究дјҡз·ЁгҖҢйғЁиҗҪеҸІиҰігҒҜи»ўжҸӣгҒ—гҒҹгҒӢгҖҖпјҚзҸҫеңЁгҒЁжңӘжқҘгӮ’е•ҸгҒҶпјҚгҖҚ
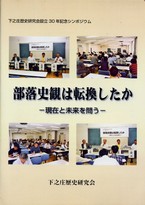 йғЁиҗҪеҸІгҒ«еӯҰгҒјгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒ®еҝ…иӘӯж–ҮзҢ®гҒ§гҒҷгҖӮйғЁиҗҪеҸІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ„гҒҫгҒ ж•ҷ科жӣёгҒ«гӮӮгҖҒиІ§еӣ°гғ»дҪҺдҪҚжҖ§и«–гҒЁжӮІжғЁеҸІиҰігҒҢе№…гӮ’гҒҚгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҰӢж–№гҒҢгҒ„гҒҫгӮҲгӮҠгӮӮгҒ•гӮүгҒ«еӨ§еӢўгӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҹжҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҖҒдёӢд№Ӣеә„жӯҙеҸІз ”究дјҡгҒҜгҖҒйғЁиҗҪеҸІиҰігҒ®и»ўжҸӣгӮ’жҸҗе”ұгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮең°е…ғгҒ®иіҮж–ҷзҷәжҺҳгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®йғЁиҗҪеҸІгӮ’жү№еҲӨгҒ—гҒҰж–°гҒҹгҒӘиҰӢж–№гӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жҙ»еӢ•гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«еӣӣеҚҠдё–зҙҖгӮ’йҒҺгҒҺгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжң¬жӣёгҒҜгҖҒиЁӯз«Ӣ30е‘Ёе№ҙгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹиҮӘдё»зҡ„ж°‘й–“з ”з©¶еӣЈдҪ“гҒҢй–ӢеӮ¬гҒ—гҒҹгӮ·гғігғқгӮёгӮҰгғ гҒ®иЁҳйҢІгҒ§гҒҷгҖӮеҘҲиүҜзңҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёӢд№Ӣеә„жӯҙеҸІз ”究дјҡгҒ®пјңжҢҒз¶ҡгҒҷгӮӢеҝ—пјһгӮ’иіһиіӣгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йғЁиҗҪеҸІгҒ«еӯҰгҒјгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒ®еҝ…иӘӯж–ҮзҢ®гҒ§гҒҷгҖӮйғЁиҗҪеҸІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ„гҒҫгҒ ж•ҷ科жӣёгҒ«гӮӮгҖҒиІ§еӣ°гғ»дҪҺдҪҚжҖ§и«–гҒЁжӮІжғЁеҸІиҰігҒҢе№…гӮ’гҒҚгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҰӢж–№гҒҢгҒ„гҒҫгӮҲгӮҠгӮӮгҒ•гӮүгҒ«еӨ§еӢўгӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҹжҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҖҒдёӢд№Ӣеә„жӯҙеҸІз ”究дјҡгҒҜгҖҒйғЁиҗҪеҸІиҰігҒ®и»ўжҸӣгӮ’жҸҗе”ұгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮең°е…ғгҒ®иіҮж–ҷзҷәжҺҳгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®йғЁиҗҪеҸІгӮ’жү№еҲӨгҒ—гҒҰж–°гҒҹгҒӘиҰӢж–№гӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жҙ»еӢ•гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«еӣӣеҚҠдё–зҙҖгӮ’йҒҺгҒҺгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжң¬жӣёгҒҜгҖҒиЁӯз«Ӣ30е‘Ёе№ҙгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹиҮӘдё»зҡ„ж°‘й–“з ”з©¶еӣЈдҪ“гҒҢй–ӢеӮ¬гҒ—гҒҹгӮ·гғігғқгӮёгӮҰгғ гҒ®иЁҳйҢІгҒ§гҒҷгҖӮеҘҲиүҜзңҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёӢд№Ӣеә„жӯҙеҸІз ”究дјҡгҒ®пјңжҢҒз¶ҡгҒҷгӮӢеҝ—пјһгӮ’иіһиіӣгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҶ…е®№гҒҜгҖҒдёӢд№Ӣеә„жӯҙеҸІз ”究дјҡгҒ®д»ЈиЎЁгҒ§гҒӮгӮӢдёҠйҮҺиҢӮгҒ•гӮ“гҒ®е ұе‘ҠгҖҢйғЁиҗҪеҸІиӘҚиӯҳгҒ®еҶҚж§ӢзҜүгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгҖҚгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒиҘҝж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгҒҜд№қе·һгғ»зҰҸеІЎзңҢдәәжЁ©з ”з©¶жүҖгҒ®з«№жЈ®еҒҘдәҢйғҺгҒ•гӮ“гҒ®гҖҢйғЁиҗҪеҸІиҰігҒҜи»ўжҸӣгҒ—гҒҹгҒӢгҖҚгҖҒжқұж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгҒҜй•·йҮҺгҒ®дҝЎе·һиҫІжқ‘й–ӢзҷәеҸІз ”究жүҖгҒ®ж–Һи—ӨжҙӢдёҖгҒ•гӮ“гҒ®гҖҢдҝЎжҝғеӣҪгҒ®иҝ‘дё–йғЁиҗҪеҸІз ”究гҒ®жҲҗжһңгҒЁиӘІйЎҢгҖҚгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ең°еҹҹгҒ«ж №гҒ–гҒ—гҒҹиІҙйҮҚгҒӘе ұе‘ҠгҒҢеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҠйҮҺгҒ•гӮ“гҒ®е ұе‘ҠгҒҜгҖҒгҖҺйӣ‘еӯҰгҖҸгҒ«йҖЈијүгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢз•°иғҪиҖ…и«–гҖҚгҒ®йӣҶеӨ§жҲҗгҒ§гҒҷгҖӮз«№жЈ®гҒ•гӮ“гӮӮжңҖеҲқгҒҜгҖҢе…ЁеӣҪеҗ„ең°гҒ§гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиЁҖгҒ„гҒҹгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖҚгҒЁиЁҖгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒж–Һи—ӨгҒ•гӮ“гҒ«жҢ‘зҷәгҒ•гӮҢгҒҰгҖҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢе…ЁеӣҪгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖҚгҒЁеӨүеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иҫәгҒ®и©ігҒ—гҒ„еҶ…е®№гҒҜгҖҒгҒңгҒІгҒЁгӮӮжң¬жӣёгӮ’зҙҗи§ЈгҒӢгӮҢгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйқһеёёгҒ«гҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒ„гӮ·гғігғқгӮёгӮҰгғ гҒ®е®ҹжіҒдёӯз¶ҷгҒҢе‘ігӮҸгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дҝқйҡңгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
B5еҲӨгҖҖ77гғҡгғјгӮё
й ’дҫЎгҖҖ700еҶҶ
дёӢд№Ӣеә„жӯҙеҸІз ”究дјҡз·ЁгҖҢйғЁиҗҪеҸІиҰігҒҜи»ўжҸӣгҒ—гҒҹгҒӢгҖҖпјҚзҸҫеңЁгҒЁжңӘжқҘгӮ’е•ҸгҒҶпјҚгҖҚ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
дә¬йғҪеәңз«ӢеҹҺйҷҪй«ҳзӯүеӯҰж Ўз·Ёи¬ӣжј”йӣҶгҖҖеў—иЈңзүҲгҖҺж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№гҖҸпјҲеңЁеә«гҒӘгҒ—пјү
 жң¬жӣёгҒҜгҖҒгҖҺиў«е·®еҲҘйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҖпјҚж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№пјҚгҖҸгҒ®гӮөгғ–гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҹҺйҷҪй«ҳж ЎгӮ„дә¬йғҪеәңз«Ӣй«ҳзӯүеӯҰж ЎеҗҢе’Ңж•ҷиӮІз ”究дјҡгҒ®з ”дҝ®гҒ§гҒ®и¬ӣжј”йҢІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј‘пјҗдәәгҒ®и¬ӣжј”иҖ…гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢзӢ¬иҮӘгҒ®иҰ–зӮ№гҒ§йғЁиҗҪеҸІгӮ’иӘһгӮӢгҖӮ
жң¬жӣёгҒҜгҖҒгҖҺиў«е·®еҲҘйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҖпјҚж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№пјҚгҖҸгҒ®гӮөгғ–гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҹҺйҷҪй«ҳж ЎгӮ„дә¬йғҪеәңз«Ӣй«ҳзӯүеӯҰж ЎеҗҢе’Ңж•ҷиӮІз ”究дјҡгҒ®з ”дҝ®гҒ§гҒ®и¬ӣжј”йҢІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј‘пјҗдәәгҒ®и¬ӣжј”иҖ…гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢзӢ¬иҮӘгҒ®иҰ–зӮ№гҒ§йғЁиҗҪеҸІгӮ’иӘһгӮӢгҖӮ
гӮӮгҒҸгҒҳ
гҖҢйғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҒЁж•ҷиӮІеҶ…е®№гҒ®еүөйҖ гҖҚ
еҗүз”°ж „жІ»йғҺгҒ•гӮ“пјҲеҘҲиүҜзңҢз«ӢеҗҢе’Ңе•ҸйЎҢй–ўдҝӮиіҮж–ҷгӮ»гғігӮҝгғјпјү
гҖҢгӮұгӮ¬гғ¬ж„ҸиӯҳгҒЁз•°иғҪиҖ…йӣҶеӣЈгҖҚ
дёҠйҮҺгҖҖиҢӮгҒ•гӮ“пјҲеҘҲиүҜзңҢдёүйғ·з”әдёӢд№Ӣеә„и§Јж”ҫдјҡйӨЁйӨЁй•·пјү
гҖҢйғЁиҗҪеҸІиҰігҒ®и»ўжҸӣгҒЁи§Јж”ҫгҒёгҒ®еұ•жңӣгҖҚ
йҮ‘дә•иӢұжЁ№гҒ•гӮ“пјҲе…ЁеӣҪеңЁж—Ҙжңқй®®дәәж•ҷиӮІз ”究еҚ”иӯ°дјҡдәӢеӢҷеұҖй•·гғ»еҪ“жҷӮпјү
гҖҢгҒ„гҒҫгҖҒйғЁиҗҪеҸІгҒҢгҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒ„гҖҚ
жёЎиҫәдҝҠйӣ„гҒ•гӮ“пјҲйғЁиҗҪи§Јж”ҫгғ»дәәжЁ©з ”з©¶жүҖпјү
гҖҢйғЁиҗҪеҸІгҒҢгҒӢгӮҸгӮӢгҖҚ
дёҠжқүгҖҖиҒ°гҒ•гӮ“пјҲй–ўиҘҝеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйғЁи¬ӣеё«пјү
гҖҢйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгӮ’гҒ©гҒҶеӯҰгҒ¶гҒ®гҒӢгҖҚ
дҪҸжң¬еҒҘж¬ЎгҒ•гӮ“пјҲзҰҸеІЎзңҢз«ӢеҢ—д№қе·һй«ҳзӯүеӯҰж Ўгғ»еҪ“жҷӮпјү
гҖҢиў«е·®еҲҘйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҚ
еұұжң¬е°ҡеҸӢгҒ•гӮ“пјҲдё–з•ҢдәәжЁ©е•ҸйЎҢз ”з©¶гӮ»гғігӮҝгғјгғ»еҪ“жҷӮпјү
гҖҢиҝ‘д»ЈйғЁиҗҪе•ҸйЎҢжҲҗз«Ӣгғ»еәҸиӘ¬гҖҚ
е°Ҹжһ—дёҲеәғгҒ•гӮ“пјҲдә¬йғҪеёӮжӯҙеҸІиіҮж–ҷйӨЁжӯҙеҸІиӘҝжҹ»е“Ўпјү
гҖҢжңҖиҝ‘гҒ®з ”究гӮ’гҒөгҒҫгҒҲгҒҹйғЁиҗҪеҸІеӯҰзҝ’гҒ®иҰ–зӮ№гҖҚ
еӨ–е·қжӯЈжҳҺгҒ•гӮ“пјҲдә¬йғҪеёӮз«Ӣж°ёжқҫиЁҳеҝөж•ҷиӮІгӮ»гғігӮҝгғјз ”究иӘІгғ»еҪ“жҷӮпјү
гҖҢгҖҺжёӢжҹ“дёҖжҸҶеҶҚиҖғгҖҸпјҚеӨҡж§ҳгҒӘйғЁиҗҪеҸІеғҸгӮ’жұӮгӮҒгҒҰпјҚгҖҚ
и—Өз”°еӯқеҝ—гҒ•гӮ“пјҲеІЎеұұзңҢеӮҷеүҚеёӮз«ӢеӮҷеүҚдёӯеӯҰж Ўпјү
A5еҲӨгҖҖ268p
й ’дҫЎгҖҖ700пјҲгҖҺиў«е·®еҲҘйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҖпјҚж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№пјҚгҖҸгҒЁгӮ»гғғгғҲгҒ§1000еҶҶпјү
дә¬йғҪеәңз«ӢеҹҺйҷҪй«ҳзӯүеӯҰж Ўз·Ёи¬ӣжј”йӣҶгҖҖеў—иЈңзүҲгҖҺж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№гҖҸпјҲеңЁеә«гҒӘгҒ—пјү гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
дә¬йғҪеәңз«ӢеҹҺйҷҪй«ҳзӯүеӯҰж Ўз·Ё гҖҺиў«е·®еҲҘйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҖпјҚж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№пјҚгҖҸж”№иЁӮзүҲ
 иҝ‘е№ҙгҖҒйғЁиҗҪеҸІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гҖҢиҝ‘дё–ж”ҝжІ»иө·жәҗиӘ¬гҖҚгҒ«гҒҹгҒ„гҒ—гҒҰгҖҢйғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҖҚгҒҢеҘҲиүҜгғ»еӨ§йҳӘгғ»дә¬йғҪгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒе…ЁеӣҪгҒ§еҫҗгҖ…гҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ з ”з©¶иҖ…гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒ©гҒҶз”ҹеҫ’гҒ«ж•ҷгҒҲгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҖҒзҸҫе ҙгҒ®ж•ҷе“ЎгҒ«гҒЁгҒҫгҒ©гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢйғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҖҚгҒҜгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҖҢйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҚгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒгҖҢж—Ҙжң¬гҒ®жӯҙеҸІгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҖҚгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«дҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒ2002е№ҙеәҰгҒӢгӮүгҖҒдёӯеӯҰж ЎгҒ®жӯҙеҸІж•ҷ科жӣёгҒ®иЁҳиҝ°гӮӮеӨ§гҒҚгҒҸеӨүгӮҸгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
иҝ‘е№ҙгҖҒйғЁиҗҪеҸІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гҖҢиҝ‘дё–ж”ҝжІ»иө·жәҗиӘ¬гҖҚгҒ«гҒҹгҒ„гҒ—гҒҰгҖҢйғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҖҚгҒҢеҘҲиүҜгғ»еӨ§йҳӘгғ»дә¬йғҪгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒе…ЁеӣҪгҒ§еҫҗгҖ…гҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ з ”з©¶иҖ…гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒ©гҒҶз”ҹеҫ’гҒ«ж•ҷгҒҲгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҖҒзҸҫе ҙгҒ®ж•ҷе“ЎгҒ«гҒЁгҒҫгҒ©гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢйғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҖҚгҒҜгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҖҢйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҚгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒгҖҢж—Ҙжң¬гҒ®жӯҙеҸІгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҖҚгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«дҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒ2002е№ҙеәҰгҒӢгӮүгҖҒдёӯеӯҰж ЎгҒ®жӯҙеҸІж•ҷ科жӣёгҒ®иЁҳиҝ°гӮӮеӨ§гҒҚгҒҸеӨүгӮҸгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжөҒгӮҢгҒ®дёӯгҒ§гҖҒдә¬йғҪеәңгҒ®е…¬з«Ӣй«ҳж ЎгҒ§гҒҜгҖҢж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҖҚгҒ®ж•ҷжқҗеҢ–гӮ’гҒҷгҒҷгӮҒгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёҖгҒӨгҒ®зөҗжһңгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒжң¬жӣёгҖҺиў«е·®еҲҘйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҖпјҚж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№пјҚгҖҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӯдё–гҒ®иў«е·®еҲҘж°‘гҒ®иө·гҒ“гӮҠгҒӢгӮүгҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҖҒиҝ‘дё–гҒ®иў«е·®еҲҘж°‘гҒ®е§ҝгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒЁгӮҠгҒҫгҒҸгҒҫгӮҸгӮҠгҒ®гҒҫгҒӘгҒ–гҒ—гҖҒиҝ‘гғ»зҸҫд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйғЁиҗҪе·®еҲҘгҒ®зӨҫдјҡе•ҸйЎҢеҢ–гҒЁйғЁиҗҪе·®еҲҘж’Өе»ғгҒёгӮҖгҒ‘гҒҹй—ҳгҒ„гҒ®жӯҙеҸІгӮ’гҖҒпјЎпј”зүҲгҒ«пј“пј’гғҡгғјгӮёгҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮйғЁиҗҪеҸІеӯҰзҝ’гҒ®гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒЁгҒ—гҒҰжңҖйҒ©гҒ®жӣёгҒЁиЁҖгҒҲгӮҲгҒҶгҖӮ
пјЎпј”еҲӨгҖҖпј“пј’гғҡгғјгӮё
й ’дҫЎпј“пјҗпјҗеҶҶ
дә¬йғҪеәңз«ӢеҹҺйҷҪй«ҳзӯүеӯҰж Ўз·Ё гҖҺиў«е·®еҲҘйғЁиҗҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҖпјҚж–°гҒ—гҒ„йғЁиҗҪеҸІгҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№пјҚгҖҸж”№иЁӮзүҲ гҒҜгӮігғЎгғігғҲгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“
й«ҳеҸ–жҳҢдәҢи‘— гҖҺеҗҢжҖ§ж„ӣиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҖҖcoming outгҒ®и»Ңи·ЎгҖҸ
 гҒ“гҒ®жң¬гҒ«гҒҜгҖҒгҖҢеӨҡж§ҳгҒӘгӮ»гӮҜгӮ·гғҘгӮўгғӘгғҶгӮЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгӮҲгҒҶгҖӮжҖ§ж•ҷиӮІгӮ„дәәжЁ©ж•ҷиӮІгҒ«гҒқгҒ®иҰ–зӮ№гӮ’гҒЁгӮҠе…ҘгӮҢгӮҲгҒҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгҒҢгҒ“гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жң¬гҒ«гҒҜгҖҒгҖҢеӨҡж§ҳгҒӘгӮ»гӮҜгӮ·гғҘгӮўгғӘгғҶгӮЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгӮҲгҒҶгҖӮжҖ§ж•ҷиӮІгӮ„дәәжЁ©ж•ҷиӮІгҒ«гҒқгҒ®иҰ–зӮ№гӮ’гҒЁгӮҠе…ҘгӮҢгӮҲгҒҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгҒҢгҒ“гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ»гӮҜгӮ·гғҘгӮўгғӘгғҶгӮЈгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ°гҒҜгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ дёҖиҲ¬гҒ«жөёйҖҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒөгӮҢгӮӢдәәгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жҰӮиӘ¬гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ第1йғЁгҖҢеӨҡж§ҳгҒӘгӮ»гӮҜгӮ·гғҘгӮўгғӘгғҶгӮЈгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҚгӮ’жӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж•ҷ科жӣёзҡ„гҒӘзҹҘиӯҳгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒйҖҖеұҲгҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҹж–№гҒҜгҖҒ第2йғЁгҒӢгӮүиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгӮүгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
第2йғЁгҖҢcoming outгҒ®и»Ңи·ЎгҖҚгҒҜгҖҒдё»гҒ«1997е№ҙгҒ®з§ӢгҒӢгӮү2000е№ҙгҒ®жҳҘгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒеғ•иҮӘиә«гҒҢгҒҫгӮҸгӮҠгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒ«гӮ«гғҹгғігӮ°гӮўгӮҰгғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸйҒҺзЁӢгҒ§жӣёгҒҚгҒҹгӮҒгҒҹж–Үз« гӮ’еҶҚж§ӢжҲҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮиҮӘеҲҶгҒҢеҗҢжҖ§гӮ’еҘҪгҒҚгҒ гҒЁж°—гҒҘгҒ„гҒҰгҒӢгӮүгҖҒй•·гҒ„жҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒЁеҗ‘гҒҚеҗҲгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒж–ҮеҢ–зҘӯгҒ®ж•ҷиҒ·е“ЎеҠҮгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«еҚҒж•°дәәгҒ®еҗҢеғҡж•ҷе“ЎгҒ«гӮ«гғҹгғігӮ°гӮўгӮҰгғҲгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҖҒз”ҹеҫ’гҒҹгҒЎгҒёгҒ®гӮ«гғҹгғігӮ°гӮўгӮҰгғҲгҒЁгҒқгҒ®еҫҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒ«жІҝгҒЈгҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
第3йғЁгҖҢпјЎпј©пјӨпјігҒЁеҗҢжҖ§ж„ӣгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒжңқж—Ҙж–°иҒһгҒ®гҖҢи«–еЈҮгҖҚгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹж–Үз« гӮ’жқҗж–ҷгҒ«гҖҒзұіеӣҪгҒ§гҒ®зөҢйҒҺгӮ„йҒҺеҺ»гҒ®жӯҙеҸІгҒ«гҒөгӮҢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒпјЎпј©пјӨпјігҒЁз”·жҖ§еҗҢжҖ§ж„ӣгҒ®й–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиҖғгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж•ҷиҒ·е“ЎгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®ж–№гҖ…гҒ«гҒ“гҒ®гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгҒҢдјқгӮҸгӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ«гғҹгғігӮ°гӮўгӮҰгғҲгҒЁгҒҜгҖҒиҮӘгӮүгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒЁеҗ‘гҒҚеҗҲгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгӮ’иЁҖиӘһеҢ–гҒ—гҖҒе‘ЁеӣІгҒ®дәәгҒ«иӘһгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҒӢгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸдҪңжҘӯгҒ§гҒҷгҖӮй•·гҒ„жә–еӮҷжңҹй–“гӮ’зөҢгҒҰгҖҒж•ҷиҒ·е“ЎеҠҮд»ҘйҷҚгҖҒдәӢж…ӢгҒҜжҖҘйҖҹгҒ«еұ•й–ӢгҒ—гҒҜгҒҳгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒеҝғгҒ®еҘҘгҒ«й–үгҒҳгҒ“гӮҒгҒҰгҒҚгҒҹгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢе °гӮ’еҲҮгҒЈгҒҹгҒӢгҒ®гҒ”гҒЁгҒҸгҖҒгҒөгҒӨгҒөгҒӨгҒЁгӮҸгҒҚгҒӮгҒҢгӮӢй«ҳжҸҡж„ҹгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжңҹеҫ…гҖҒд»ҠгҒҫгҒ§иҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеҝғгҒ®ж·ұгҒҝгҒ«еҗ‘гҒҚеҗҲгӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒ—гӮ“гҒ©гҒ•гҖҒеҫ®еҰҷгҒӘеҝғгҒ®жҸәгӮҢгҒЁз—ӣгҒҝгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒЁгӮӮгҒҷгӮҢгҒ°ж„ҹжғ…гҒ®жҙӘж°ҙгҒ«гҒ®гҒҝгҒ“гҒҫгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒқгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒе‘ЁеӣІгҒ®дәәгҒ«и©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜгҖҒгҒІгҒҹгҒҷгӮүж–Үз« гӮ’жӣёгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§иёҸгҒҝгҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒзҸ зҺүгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒ©гӮӮгҒҢеҝғгҒ®еә•гҒ«гҒ—гҒҝгҒ“гӮ“гҒ§гҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҮӘеҲҶгҒ®гҒ—гӮғгҒ№гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиЁҖи‘үгӮ’гҒЎгӮғгӮ“гҒЁдҝЎгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹиҰҡгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҜдҪ•гҒӢгӮ’гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ•гҒӣгҒҰгҖҒиҮӘгӮүгҒ®жүӢгҒ§гҒӨгҒӢгҒҝгҒ«гҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдәәй–“гҒЁгҒҜдҝЎгҒҳгӮӢгҒ«еҖӨгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶзўәдҝЎгҖӮ
гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“жӣёгҒ„гҒҹж–Үз« гӮ’иӘӯгӮ“гҒ§жё©гҒӢгҒ„гӮігғЎгғігғҲгӮ’гҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹгҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҒ«ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҖҒдёҖеҶҠгҒ®жң¬гҒҢгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҚеҚҒеҲҶгҒӘзӮ№гӮӮеӨҡгҖ…гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒІгҒЁгҒҫгҒҡгҒ“гӮҢгҒҢеҲ°йҒ”зӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгӮҸгӮҠгҒ§ж”ҜгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®гҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҒ«ж„ҹи¬қгӮ’гҒ“гӮҒгҒҰгҖӮ
2000е№ҙпј—жңҲ10ж—ҘгҖҖй«ҳеҸ–жҳҢдәҢ
гҖҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гҖҚгӮҲгӮҠ